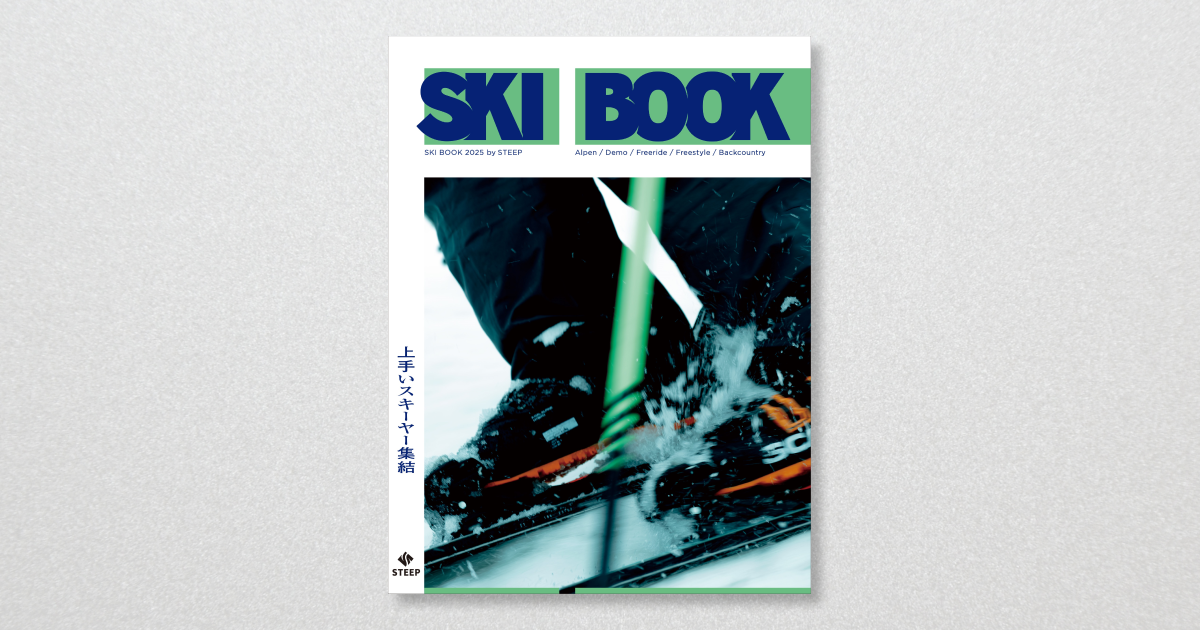文/寺倉 力 Text / Chikara Terakura
編集/STEEP編集部 Edit / STEEP
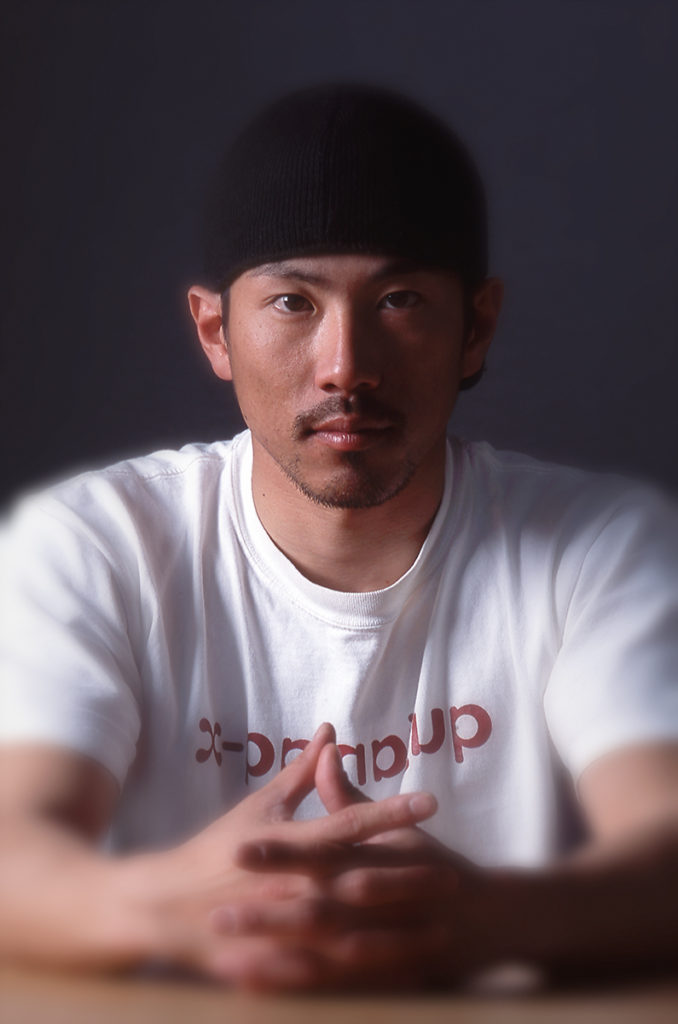
Photo / Norimichi Kameda
「プロスキーヤー」として今年20年目を迎えた児玉毅の最新インタビューをお届けしよう。26歳でアルバイトを辞めて以来、これまでスキー1本で生活してきたという。世界の雪山にシュプールを刻み、そのライディングとエンターテイメント性あふれる表現で多くの滑り手を魅力してきた彼のモチベーションの源に迫ってみた。インタビューアーは「Fall Line」編集長の寺倉力。児玉とは20年来の付き合いである。
INDEX
- 少雪&コロナと苦しめられた19-20シーズン。児玉毅はいつまで滑っていたのか?
- なぜ、児玉毅は原稿が上手いのか?
- 児玉毅がプロスキーヤーになるまでの話
- 冒険的な遠征が一段落してから、児玉は何をしていたのか?
少雪&コロナと苦しめられた19-20シーズン。児玉毅はいつまで滑っていたのか?
──先シーズン(19-20シーズン)の滑り納めはいつ頃でした?
4月の頭です。それまでは撮影もあったし、比較的普通に滑っていたんですよ。で、いよいよ山の活動も自粛すべきだと風潮が色濃くなってきた段階で、一回スキーを整理しました。その後、6月に入ってから十勝と大雪に3回ほど残雪を滑りに行き、自分としてはそれを滑り納めと位置づけています。
──自粛期間中は何をしていたの?
自宅で家族と過ごしていました。まあ、ここであがいても、できることは限られていましたからね。子どもたちも登校できないし、一緒になって勉強を見てあげたりして。子どもたちも大きくなってきたし、これから先のことを考えても、家族とじっくり向き合えたのは貴重な機会だったと思っています。
──毎年恒例の「地球を滑る旅」も中止にしたと聞いてますが。
そうなんですよ。本来であれば3月の3週目には出発しているはずでした。行き先も決めて準備も進めていたんですけどね。フォトグラファーの佐藤圭君とも早い時期から話はしていて、最終的に2月末の時点で延期と決めました。
──今年はどこを予定していたの?
え~とですね。それは例によって秘密です。帰国するまで決して行き先を人に教えないのが僕らのルール。たとえお世話になった関係者でも、スポンサーでもです。わかっていて訊きましたよね?
──さりげなく差し込んだつもりだったんだけど、さすがにガードが堅いね(笑)。
そこはいちおう(笑)。
なぜ、児玉毅は原稿が上手いのか?
──前から訊きたかったことなんだけど、なぜ、児玉毅は原稿が上手いのかという点。滑り手のなかでは圧倒的に読ませる原稿が書ける。それはなぜなんだろう?
いやぁ、それこそ「BRAVOSKI」を始め、昔からスキー雑誌で原稿を書かせていただいたおかげです。編集部のみなさんにいろいろ教えていただきましたから。
──初期からの編集担当として言わせてもらえば、タケの原稿は最初からぐいぐい読めたし、編集部内でもそれが話題だった。なんでこんなに上手なんだろうって。
そうでしたか?
──そうだよ。タケの原稿に大々的な赤字を入れた記憶はないし、文章的な点でダメ出ししたこともないと思う。テーマや構成のディレクションはしたけどね。
そうかもしれませんね。文章的にはあまり指摘されなかったかな。

──では、なぜ書けたのかな。苦労している様子もなく、むしろ楽しげだった。
実はですね、子どもの頃から書くことが好きだったんですよ。だから、よく文章を書いてました。小学校の頃は、お節介にも勝手に学級新聞を書いて、それをみんなに配ったりしてました。ちょっと変わった子だったかもしれません。あとは、高校生のときには推理小説も書きました(笑)。
一時期ハマりましたね。書いてて楽しいですよね。途中でいくつも伏線を張って、それを回収していくのがおもしろくて……。
──ということは、本もよく読んでいた?
読みました。本は好きでしたね。オヤジが国語の先生だったんですけど、読みやすくておもしろい本をよく買って帰るわけですよ。もちろん、マンガも当たり前に好きでしたけど、活字のおもしろさにも気がつくことができた。それが小学校高学年くらいかな。それからはよく本を読むようになったんです。
──どんな本を読んでいたの?
まずは『十五少年漂流記』のような冒険物です。そのあとミステリー系にいったり、歴史物にいったり、ノンフィクションにいったり。いろいろ読みあさりました。海外の詩集とか、堅苦しい海外の文学系も読みましたよ。山でゲーテやヘッセとかも。山と本は相性が良かったから、山に登るようになってからさらに進んだ感じです。
──やっぱりね。いい文章を書くには読書が欠かせないなんだよね。
それがドルフィンズに入ってからの一時期は、ちょっと忘れかけていたんです。あまりにスキーに没頭しすぎて読書どころではなかった。それからしばらく経ってスキー雑誌を読み込むようになって、それこそ「BRAVOSKI」で寺倉さんの原稿も読んだし、庄司さんの連載も読んでいましたよ。自分が好きなスキーの話を書くのっておもしろそうだよなと、それであらためて思い出したんです。これが表現なんだよなって。
──まずは庄司克史の連載「ゲレンデ外だド」があって、その後を引き継ぐように児玉毅と佐々木大輔の連載が始まった。それが15年以上も前の話かと思うと感慨深い。今思えば、タケのほうはいきなり長文でのスタートだったけどね。
あの頃、「BRAVOSKI」を楽しみにしていた人って多かったと思いますよ。特に連載やコラムがおもしろかった。世代的なものもあると思いますね。僕らに近い年代が多いと思うんですけど、みんな雑誌世代ですよね。
──編集部としてもけっこう連載に力を入れていたしね。
あの頃は、なにかギトギトと匂いを放っているページがけっこうありましたよね。僕はあれが好きだったな。逆に今の「BRAVOSKI」には、あの頃のようなプンプン臭ってくるページが少ないですね。なんて言うか、ちょっと小ぎれいにまとまってる感じがします。
児玉毅がプロスキーヤーになるまでの話




児玉毅は1974年7月、札幌市手稲区で生まれた。スキーを始めたのは4歳のときで、自宅から近いテイネのスキー場(現、サッポロテイネ)によく通った。だが、中学高校時代はスキーそっちのけで、もっぱら部活のバレーボールに熱中していたという。
本人曰く「慢性五月病のような」大学生活を送っていたある日のこと、「スキーインストラクター募集」のチラシを目にする。そうして門を叩いたのが、テイネハイランドを本拠地としていた三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクールだった。
そこから児玉は一人前のスキーインストラクターを目指して本格的なスキー修業を始める。その時点で19歳。スキーを活動の中心に据えるには遅いスタートといっていいだろう。競技経験もないスキー好きのイチ大学生が、後にプロスキーヤーとしてシーンをリードする存在になるとは、このとき誰も予想していなかったに違いない。
児玉がテクニカルでストロングなスキーヤーへと急成長を遂げた要因は大きく3つある。ひとつは全国屈指のハードバーンが目白押しのテイネハイランドという練習環境であり、ふたつ目は「よく滑ることと、よく酒を呑むことが美徳」とされた三浦&スノードルフィンズの自由闊達な気風。そして、三つ目は佐々木大輔という超イケイケなライディングパートナー&ライバルの存在である。

高校を卒業したばかりの佐々木大輔が研修生としてドルフィンズに入門してきたのは、児玉の2年後だった。以後数シーズンというもの、この2歳年下の仲間と互いに競い合うように滑り狂った。そのハードワークの蓄積が、後のプロスキーヤーの下地になっている。
こうして互いに切磋琢磨し合うことで、児玉と佐々木はフリースキーシーンの表舞台にその名を知られるようになっていく。エビスフィルムスの「icon」シリーズは常に彼らを軸に据え、各スキー雑誌の表紙や誌面も次々に飾る。折から火が付いていたバックカントリースキーへの注目度もそれを後押ししていた。
児玉毅プロフィール
1974年 札幌市手稲区に生まれる
1993年 三浦雄一郎&スノードルフィンスキースクール入門
1996年 第一回ジャパンエクストリームチャンピオンシップ出場
1998〜1999年 コロラド州クレステッドビュートにて単身スキー武者修行
2000年 北米最高峰マッキンリー(現、デナリ)山頂からスキー滑降(なまら癖ーX)
2001年 北クリル諸島探検スキー(なまら癖ーX)
2001年 「icon of what they are」(EBIS Films)シリーズ1作目リリース
2002年 南米大陸単身スキー放浪
2003年 グリーンランド シーカヤック&スキー遠征(なまら癖ーX)
2004年 ネパールヒマラヤ・メラピーク山頂からスキー滑降
2005年 結婚
2005年 世界最高峰エベレスト登頂
2007年 北海道スノースポーツ実行委員会発足
2008年 第一子誕生
2008年 ヒマラヤ・西ネパール未踏峰スキー滑降
2010年 第二子誕生
2012年 地球を滑る旅1「レバノン」
2013年 10年目のグリーンランド遠征(なまら癖-X)
2014年 地球を滑る旅2「モロッコ」
2015年 地球を滑る旅3「アイスランド」
2016年 地球を滑る旅4「カシミール」
2017年 地球を滑る旅5「ロシア」
2018年 地球を滑る旅6「ギリシャ」
2019年 地球を滑る旅7「中国」
冒険的な遠征が一段落してから、児玉は何をしていたのか?
──今回のインタビューに際して、いくつか確認しようとオフィシャルウエブサイトを開こうとしたら、すでになかった。
あ、はい。そうなんですよ(汗)。いろんな人からのアドバイスをいただいて始めたオフィシャルウェブサイトでしたが、なかなか更新できなくて。そのうちフェイスブックのほうにシフトしていき、サイトは放置されているという……。最近、インスタグラムも始めたので、ぜひみなさんチェックしてみてください。

──児玉毅のこれまでの歩みをザックリ見てみると、まずはドルフィンズでのスキー修業時代があり、佐々木大輔や山木匡浩らとのなまら癖ーX遠征時代があり、そして、なぜかエベレストに登頂。そこから「地球を滑る旅」(2012年スタート)までは少し間がある。結婚してエベレストに登って、子どもが生まれて、それで少し落ち着いた感じ?
そうです。まさにエベレストが終わった頃から、自分の生活環境が大きく変わったんですよね。結婚して、子どもができて……。ちょうどスキーが大きく落ち込み始めた頃で、スキー場もいくつか潰れ始めていました。果たしてプロスキーヤーとしての仕事ってどうなの? スキーの将来は? って考え込んだ時期でした。それもあって、仲間たちと「雪育」という活動を始めたんです。
──それが、2007年の「北海道スノースポーツ実行委員会」かな?
まさにそうです。スキーやスノーボードはこんなにも魅力的なのに、なぜ人気が下降するのか。まだ世の中に伝わっていない部分があるんじゃないかと。それなら自分たちにできる範囲でアクションを起こそうということで、いろいろな仕掛けを始めたんです。
たとえば、僕らとコラボレーションしてなにかやりましょうと、学校関係やアート関係など異分野の人たちのところに飛び込んでいって話を持ちかけました。一緒にアートイベントを開いたり、雪上でいろいろなミーティングを開いたりとか、何でもやりましたよ。
おかげで人脈も広がって、直接的にも間接的にもいろいろなお話をいただきました。僕らのようなフィールドの人間がアクションを起こすことが大事だと思って、5年間くらいはありとあらゆることを仕掛けまくったんです。
──「Fall Line 2007」に寄稿してくれたコラムをよく覚えています。札幌市が行政の中心軸にスノースポーツを据えたという近未来的SFストーリー。ははぁ、こんな物語も書くんだと感心しつつ、タケがスキー文化に強い関心を向けていることがよく伝わってきた。で、その後の「雪育」活動はどう進展していくの?
もちろん今も継続しています。北海道ローカルではありますが、井山敬介君や佐々木明君が中心になっている「LOVE SKI HOKKAIDO」というテレビ番組もこの活動から生まれたものですし、学校や学会、教育関係の集まりで話をさせていただくこともあります。ただ僕自身は、以前ほど積極的には仕掛けなくなっています。個人的には、ちょっと足踏みしている状態ですね。

──なぜ足踏み状態なの?
そうですね。始めた当初はスノースポーツの発展とそれを取り巻く環境整備のために、かなり大きなイメージを抱いていたわけですよ。今のスキー・スノーボード業界やこれから続く若い人たち、それに僕らの子どもたちのためにと。
ところが、この活動に本気で取り組むほど、僕が本来続けたかったスキーヤーとしての活動とは違う方向に行きそうな感じだったんですよ。もちろん、当初の気持ちがないわけではないのですが、ちょっとバランスを考えなくちゃいけないかなって。
たとえば、大きな企業や行政の人たちからは、スキーをしない人向けのイベントを求められました。スキーはハードルが高いから、「雪育」としては雪遊びを中心としたほうがいいんじゃないかと。そういう方向になっていくんですよね。で、実行部隊の中心で動いていた僕は、スキーを抑えて、雪遊びに勢力を傾けざるを得なくなっていく。
──スキーを広めたかったのにね。
そうなんですよ。あとは活動の規模が大きくなるにつれ、相手が大企業や行政という大きな組織になっていき、それこそ北海道知事と会って話をしたりと、ますます政治的な動きになっていっていくんですね。まあ、知事まではいかなかったんですけど、このまま進むとどうしても活動はそういう方向になるわけですよ。
──そういう活動に力を注ぐ元アスリートも少なくないけどね。
僕はあくまで現役ですし、やはり滑ってナンボのスキーヤーなんですよ。スキーをするという原点を忘れてはいけない。雪の上のいるときが一番幸せで、三浦雄一郎先生が今も現役で滑っているように、そこは一番なくしてはいけない聖域なわけです。
それで原点に帰ったというか。自分にとって何が大事なのかをあらためて考えた結果、背伸びをせず、地に足を付けてやっていこうというスタイルに戻したんです。
ただ、スノースポーツのための啓蒙活動が大事なことには変わりはないので、手の届く範囲での活動や応援は続けながら、やはり、当たり前なんですけど、僕のメインの活動はスキーヤーである、というわけです。

後編に続く