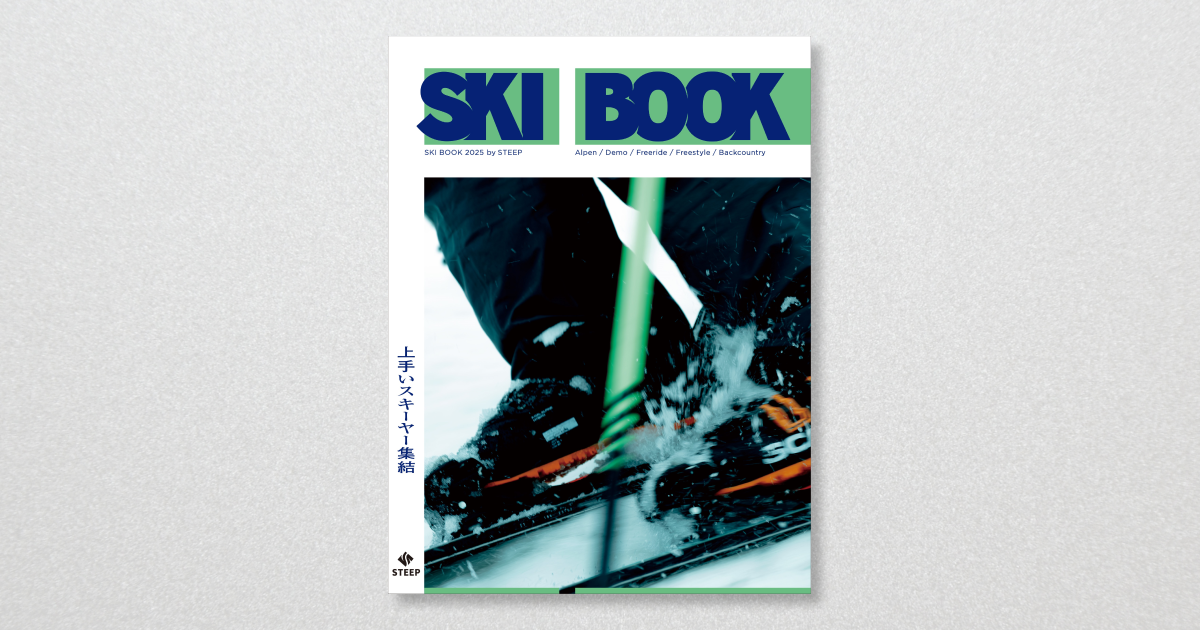雪山でのリスクを回避して安全にバックカントリーを楽しむ
管理されたスキー場と異なり、自然のままの雪山には多くのリスクが潜んでいる。ひとりで行動をするのは原則として避けるべきだし、かといって一緒に行く友人や知人が危険を回避してくれるものでもない。ガイドクラブは、バックカントリーをやったことがない人はもちろん、初めて行く場所での行動に、不安や障害があってもそれをカバーしてくれるのだ。
バックカントリーガイドは雪山の行動において、可能な限りの安全を確保してくれる。日本山岳ガイド協会 スキーガイド(以下JMGA)資格をもったガイドは、常日頃から訓練を重ね経験を積んでいるからこそ、ガイディングのスキルは総じて高い。それに生粋のスキーヤー・スノーボーダーであり、滑るのがとにかく好きな人ばかりだ。
バックカントリーではガイドといるから滑ることに集中できる

ガイドツアーに参加する最大のメリットは滑ることに集中できることだ。滑り出す斜面まで疲れにくい歩き方もレクチャーしてもらえたり、滑る際には雪の状況に応じた滑り方のアドバイスももらえたりもする。たとえコンディションが悪くても、地形や気象条件を知り尽くすガイドによって、自分たちでは当てることが難しい気持ちよく滑れる斜面にもたどり着ける。現場に通い詰めているガイドだからこそ持ちうる情報によって、その日もっとも安全でかつ最高の斜面を案内してくれるのだ。
また、時期を変えていろいろな場所のガイドクラブに行くことで、その地域の雪や地形の特長が頭に入るし、人それぞれの安全マージンのとり方を学ぶことができる。だから、ガイドクラブに入ったら、率先してガイドの行動を観察するのがいい。フィールドに着いたらどんなことをしているのか、スキンをつけるときにバックパックはどこに置いているのか、斜面を登るときはどんなルートを選んでいるのかなど。一つひとつの行動には各ガイドなりの理由がある。それを自分のなかで噛み砕いて理解することで、自分のバックカントリー知識や経験となるのだ。
バックカントリーのガイドクラブってどんなところ?

- ファットスキーを持っていないけど大丈夫?
-
レンタルも利用できる!
技術があれば道具の種類を問わずパウダーは滑れる。ただ、ハイシーズンの深い雪などを快適に楽しむなら迷わずレンタルをしよう。ガイドクラブのなかにはスキーのレンタルを行っているところもあるのでそれを利用するのがいい。
ビンディングは登高できるタイプのものが望ましいが、なくてもスノーシューがあるから、スキーをかついで登ることができる。
- 装備はなにが必要? 滑る道具だけではダメ?
-
ガイドツアーでもセーフティギアが必須。
アバランチビーコン、シャベル、プローブの3点セットはツアーでも欠かせない。持っていなくてもツアーを主催しているガイドクラブはだいたいレンタルを揃えていることが多いから安心。なかにはバックパックやスキンやスノーシュー、滑走用具のレンタルを用意しているガイドクラブもある。
- 滑走用具以外になにを用意したら良い?
-
滑走用具とセーフティギア以外に必要なギアは以下の通り
- バックパック…スキーやスノーボードが取り付けられる機能を持ったもの
- 行動食…休憩時間や行動中に食べやすいもの。コンビニで買えるおにぎりやパンなどで十分
- 飲み物…保温できる水筒に温かい飲み物がベスト。ペットボトルの水は厳冬期は行動中に凍ることもあるので注意
- ゴーグル、サングラス…普段ゲレンデを滑るときに使っているもので十分。サングラスは登るときに使う。ゴーグルやサングラスは予備を用意しておくのが望ましい
- 服装…普段ゲレンデで滑っているものでも十分。ただし速乾性のあるベースレイヤー、フリースなど保温性のあるミッドレイヤー、防水透湿性を備えたアウターウエアがあるとベスト。ビーニーやバラクラバ、ネックチューブなどもあったほうが無難
上記のものは事前に参加前に用意したほうが良い。バックパックはレンタルをしているところもあるので事前に確認するのが良い。
- セーフティギアを使ったことがない
-
ツアー前に使い方の講習会がある
レンタルで借りたギアも使い方がわかなければ意味がない。多くの初心者向けツアーでは、ツアーに出る前に道具の使い方を練習する。とくにビーコンを雪に埋めて探す"ビーコンサーチ"はリピーターツアーでもツアー前に練習するのが常だ。
- 滑れるかどうか不安…
-
スキー場の斜面をコントロールして滑れれば楽しめる!
ツアーに申し込む際、バックカントリーの経験やスキー技術などを伝える項目があり、その回答をもとにグループ分けされるため、エキスパートと初心者が同じグループになって行動することは稀だ。
また、初めてガイドに参加する人向けのツアーも用意されており、条件が整っていれば、ほぼ誰もが気持ちよくパウダーを滑ることができる。ただし、ガイドクラブによっては初心者向けツアーを催行していないところもあるので、申込み時にツアーの内容をしっかり確認しておきたい。

- 行動時間やハイク時間はどれくらいなの?
-
はじめて参加するツアーの場合、行動時間は平均4〜5時間、ハイク時間は平均1時間半ほど
滑る山域やツアー内容によって行動時間やハイク時間は大きく異なる。はじめて参加する人向けのツアーは、ゆっくりと余裕を持った時間を設定しているので安心していい。
- ハイクアップが想像つかない。登れなかったらどうしよう…
-
息が切れないペースで登れば、まず大丈夫!
ガイドツアーでは多くの場合リードガイドとテールガイドの2名体制が多い。リードガイドはグループの体力差や体格など考慮して行動範囲や登る時間、休憩時間などを調整してくれる。そのため遅れても置いていかれることはないので安心してほしい。
自分のペースがわからないのは初心者ならば当然だ。目安は登っているときに息が切れたらペースの早い証拠。どれだけゆっくりでもいいから止まらない速度で登り続けるのが基本。他の人に迷惑にならないよう頑張って歩かないと、と自分の体力以上に頑張ることは避けたい。
ほかにも疲れにくいバックパックの背負い方やストックワークはある。初心者ツアーではそれらのノウハウを伝えながら催行するので、まずはそこから参加を考えたい。

- 絶対に遭難しない?
-
バックカントリーでリスクを完全にゼロにすることはできない
"絶対ない"は言い切れない。ツアーではゲストとガイドが協力しあって、リスクを軽減していく。ゲストは自分の判断や都合で滑ることはないし、ガイドは危険を回避しながらゲストが最大限に楽しめるルートを導く。
バックカントリーではなにが起こってもいいように常に危険に対して意識を向けることが必要だ。 雪崩、転倒や滑落、クラックやスノーブリッジ、立ち木・岩・倒木などの障害物、気象条件など、バックカントリーにはさまざまな危険が存在する。
- ツアー参加前にガイドグラブの人にいろいろ教えてもらえる?
-
疑問点や不明点は参加前になるべく解消したほうが良い
ほとんどのガイドクラブはホームページを持っており、そこから問い合わせができる。いまはホームページからのコンタクトをはじめ、メール、SNSなどさまざまな方法で気兼ねなく疑問や不安を拭う手段がる。電話で聞くのも有効な手立てだ。ただ、土日の日中や夕方はガイド中が多いため、その時間帯は避けたほうがいいだろう。

STEEPではエリア別に全国のバックカントリーガイドクラブを紹介。バックカントリーに行く際の参考にしてほしい。