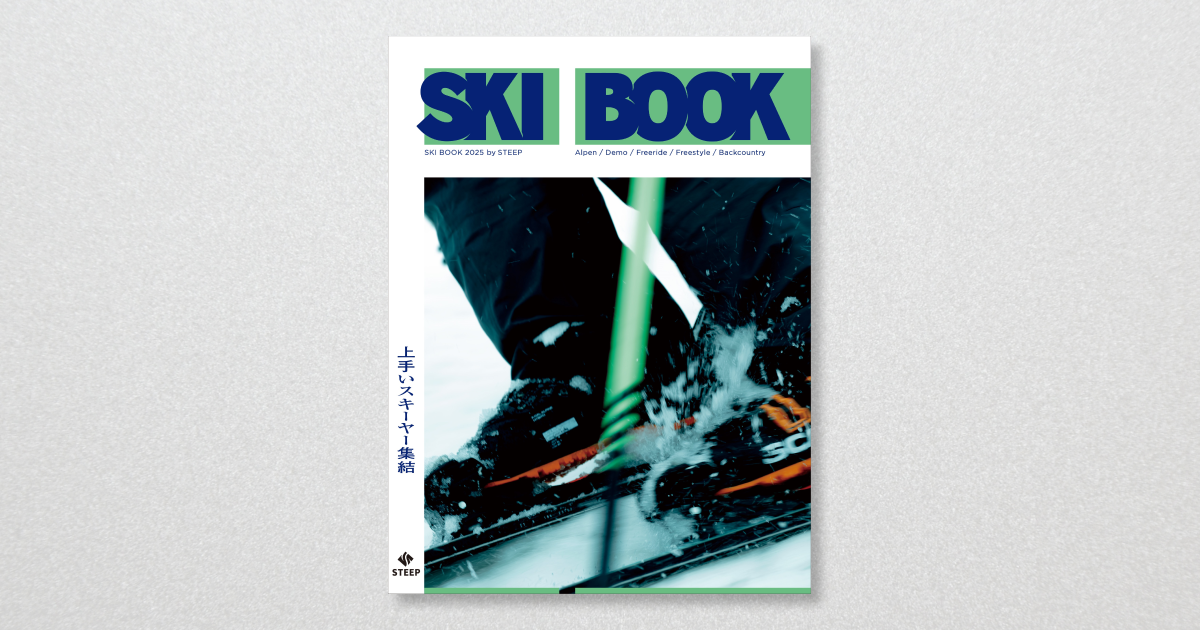このシリーズは、日本のスキー場をより詳しく、マニアックに知るためのあれこれを、さまざまな観点から解説していくものだ。第3弾は、早いシーズンのスタートをサポートし、雪不足問題をフォローしてくれる降雪機&造雪機がテーマである。後編では、これらを駆使してどこよりも早いシーズンインを実現するスキー場や、その背景など、降雪機&造雪機をめぐる興味深い部分を紹介したい。
![]() 前編はこちら
前編はこちら

10/30(金)Open! 例年、日本一オープンが早いスノータウン Yeti(イエティ)の舞台裏
2020年10月30日(金)のオープンを発表した静岡県の「スノータウンYeti(イエティ)」今年も「日本一早くオープンするスキー場」という栄えあるタイトルをキープ。'99年以降どこにも、このタイトルは渡していない。毎年、オープン日の模様は各メディアで取り上げられ、テレビ中継が入る。そんなニュースを見たことのある人も多いだろう。
かつて「日本ランドHOWスキー場」という名称だったが、「スノータウンYeti」と改名後は特に早期オープンに力を入れるようになった。スキー場がある富士山の麓は、真冬にはマイナス10℃程度に冷え込むこともあるが、雪はあまり降らない。そのため、造雪機・降雪機なくしてはスキー場の運営は事実上不可能だ。早期オープンの立役者こそ、造雪機なのである。
ベースからゲレンデの中腹まで計4台の造雪機があり、例年オープンの約10日前から24時間体制となり、オペレーターが三交代での雪造りが始まる。ただ今10/30日のオープンに向けて作業の真っただ中、造雪機は24時間フル稼働だ。1日に使う水の量は約500~600トンだという。水は約1ℓが1kgなので、500トンなら50万ℓ。想像もつかないくらい大量に水を使うのだ。
造雪機を使ったコース作りのプロセスとして、一度にコース全体を覆う雪は造れないので、造った順に山状に盛り上げておく。晴れて気温が高くなると古いものは下から解けていってしまう。それを防ぐためにカバーで覆って直射日光が当たらないようにするが、やはり山は少しずつ小さくなる。雨風、台風も天敵だ。
10/30(金)オープン時にはAゲレンデ(約1000m、高低差約150m)が滑れる予定。ちなみに、こちらは2018年のオープン日、10/25日のドローン映像だ。
’20-21シーズン、日本で2番目にオープンする軽井沢プリンスホテルスキー場は
11月3日(火・祝)、長野県内では最速、日本でも2番目に早いオープンとなる軽井沢プリンスホテルスキー場。Yetiに並んでシーズンインの代名詞的な存在だ。10月10日(日)より造雪機8基のフル稼働が始まり、オープン時には全長約400mのくりの木コース、プリンスゲレンデが滑走可能になる予定という。
1日約450トン、10/10日の作業開始からオープンまでの24日間で約6,000㎥の雪を造る。オープンまでは気温に関係なく使える造雪機の出番だ。営業開始後も継続的に造雪作業を行い、年内に全9コースのオープンを目指す。
軽井沢プリンスホテルスキー場は、造雪機8基に加えて、ファンタイプの降雪機を実に195基も所有しているとか。10~11月は造雪機で雪作り、12月半ばから降雪機に切り替えていくという。

すごい働きをしてくれる降雪機・造雪機って一体いくらなの?
雪のまったくない状態からスキーが滑れる場所を創り出し、ひいてはスキー場まで成立させてしまう驚異のマシンたちは、一体いくらぐらいするのか?
●ファンタイプの降雪機
ファンタイプの降雪機はマシンの単価は高いが、一気に大量に雪を降らせることができ、エネルギー効率もいい。大きく電気で動くものと油圧タイプと2つある。電気を使うタイプの価格の目安は1基600万円(参考価格)、油圧タイプはどこへでも移動できるメリットの分、1基1,300万円(参考価格)とかなり値が上がる。耐久年数が長く、数十年前の機種も現役で稼働している。
●ガンタイプの降雪機
ガンタイプの降雪機は、マシンの単価の目安は1基150万円ほど(参考価格)。ファンタイプより圧倒的に低価格だ。高温時(マイナス1℃~3℃程度)でも安定した仕事ができるが、大量の空気が必要でランニングコストがかる。また、一機あたりの能力的に台数を多く設置する必要がある。

しかし「スティックタイプ」「ローエアータイプ」と呼ばれる新型では、省エネ化が実現し、コストをめぐる状況はマシンの進化とともに変化している。

●造雪機
造雪機のランニングコストは降雪機のそれと比べて格段に高額。50トンタイプでプラント1台おおよそ9,000万円(参考価格)というから驚きだ。
水を確保しないと人工雪は造れない
人工雪の材料は水である。大量に雪を降らしたり、造ったりするのは大量の水がいる(一機につき1分で数百ℓ)。
リフトに乗っていて、「うあ、冷たそうだな」「あそこに落ちたらイヤだな」と思って見過ごしているあの人工的な池に溜まっている水こそ、人工雪の源だ。あくまで人工池なのでその水は、主に近くの沢などから引っ張ってくる。井戸水の場合もある。
それにしても、寒いスキー場でなぜ、あの貯水池の水は凍らないのだろう? もちろん、それは凍らないようにしているからだ。中をポンプで撹拌して凍結を防いでいるのだ。新規で降雪機や造雪機を導入しようとした場合、一苦労なのがこの貯水池と水の確保だ。スキー場は原則、山の上にある。となると、近くの沢は細く、水は決して潤沢ではない。また、沢の水を勝手に引く訳にもいかない。そうした、物理的問題、社会的条件をクリアして、初めて人工雪が現実のものになるのだ。
こんなにお金がかかっているなんて!
上記で示した「いくら」はマシンのみの話。造雪機や降雪機を稼働させるには、水や電気の確保の問題もある。そのためスキー場ごと、コースごとにかかるコストは大きく異なる。新たに設置する場合は、そうした部分での巨額な費用を見積もらなければならない。また、メンテナンス代も必要だ。
ちなみに降雪機で雪を降らすとかかる費用は、7~8円/㎥、造雪機だと40円/㎥。いかに造雪機のランニングコストが大きいかがわかる。よって、雪が造れない温度・湿度の時は造雪機、雪が造れる条件下では降雪機と使い分けるのが経費的に得策という。
ちなみに、軽井沢プリンスホテルスキー場の造雪機8基(50t/7基+100t/1基=計450t/8基)を1日稼働させるとランニングコストは40万円ほどという。オープン準備に造雪機8基を使って24日間かかることを単純計算すると880万円となる。
軽井沢プリンススキー場では、例年12月の半ばには降雪機に切り替えていくとか。
人工雪への依存度の高いスキー場
上記のYetiや軽井沢プリンススキー場に限らず、国内には降雪機、造雪機への依存度が高いスキー場は多くある。基本的には、“気温が冷え込むものの雪はあまり降らない”という気象条件のところだ。
樫山工業のお膝元である佐久平にある、佐久スキーガーデン「パラダ」は、高速道路に直結という唯一無二の環境。ここも斜面のみ雪があるという場合が多い。

中央道からアクセスする八ヶ岳方面のスキー場の多くもこの系統だ。また、中京や関西のスキー場も造雪機・降雪機の力で運営しているケースが多い。
逆に100%天然雪をうたっているスキー場もある。長野県の野沢温泉がその代表格で、白馬コルチナや奥志賀高原も同様だ。一方で、新潟県のかぐらのような、豪雪のあるスキー場でも、営業を安定させるためか、降雪機を設置している場合もある。
まとめ
シーズンの早期スタートを支え、安定したスキー場運営をサポート、雪不足問題もフォローしてくれる、すごい縁の下の力持ち、降雪機&造雪機。早いシーズンインにかかる費用やエネルギー、そして関係者の労力は想像を絶するものだ。そのおかげで、待ち焦がれていたシーズンがいよいよ始まる!
さぁ滑りに行こう!

取材・写真提供/樫山工業株式会社、軽井沢プリンスホテルスキー場、スノーシステムズ株式会社、 スノータウンYeti(五十音順)
文/ミゾロギ・ダイスケ
編集/STEEP編集部
出典:2017 BRAVOSKI vol.2より再編集
[Writer Profile] ミゾロギ・ダイスケ Daisuke Mizorogi
BRAVOSKI編集部員として20年以上に渡りスキーに携わる。モーグルの取材歴は90年代より、スキー場ガイド分野でも経験が豊富にある。一方で、サブカルチャーとスキーを融合させた、既存のスキー雑誌にはない型破りな企画を数々生み出してきた。現在は、「昭和文化研究家」という肩書きも冠しつつ、スキー以外にもさまざまなジャンルで執筆や編集活動を行う。アウトドアな世界ではもっともインドアな位置に、インドアの世界ではもっともアウトドアな位置に立脚している。
https://www.d-mizorogi.com/
※合わせて読みたい「スキー場マニアへの道」シリーズ